先日、ドライカースの著書「勇気づけて育てる」を読んでいて、ある箇所にふと疑問を感じました。それは、「子どもたちがすすんで正しい行動をするように仕向ける」といった表現がたびたび出てくる点です。
「仕向ける」という言葉、なんとなく「操作する」とか「自分の思い通りに動かす」といったニュアンスを感じませんか? でも、私たちが学ぶアドラー心理学の大前提には、「相手を変えようとしない」という考え方があります。
「あれ?これって、矛盾してるんじゃないかな?」
最初はそう思ったんです。アドラー心理学では、他者の課題に土足で踏み込まず、相手の主体性を尊重することが重要だと教わります。それなのに、「仕向ける」って、なんだか相手の自由を奪うような、一方的な働きかけのようにも聞こえてしまって。
疑問を解きほぐすための、私なりの「読み替え」
この疑問が頭の中でぐるぐるしていたのですが、色々と考えているうちに、一つの解釈にたどり着きました。それは、ドライカースが使う「仕向ける」という言葉を、「支援する」と頭の中で変換して読み進めるということです。
この読み替えをしてみると、不思議なほどスッと腑に落ちたんです。
たとえば、子どもがなかなか部屋を片付けない時。 「片付けなさい!」と一方的に命令するのは、まさに「仕向ける」のネガティブな側面かもしれません。でも、ドライカースが意図しているのは、そうではないはず。
- 「部屋がきれいだと、好きなものもすぐ見つかって気持ちがいいね」と声をかける。
- 「一緒に少しだけ片付けてみようか?」と、行動を共にすることで安心感を与える。
- 片付いた部屋で過ごすことのメリットを、具体的な体験として共有する。
これは、決して子どもを強制的に動かしているわけではありませんよね。むしろ、子どもが「自ら片付けよう」という気持ちになれるよう、優しく働きかけ、環境を整えているんです。
それでも「仕向ける」=「操作する」意図を感じるかもしれませんが、確かにそういう意図はないに越したことはありませんが、アドラー心理学は「結局している行動が大切」とも考えているので、たとえ心の中でそういう意図があったとしても、やっぱり「支援する」行動が大切なんだろとも思います。
心の中で「操作する」意図があったとしても、「支援する」行動を選択できたということは、とても重要なことだと思います。
「支援する」という言葉が持つ、温かい響き
「仕向ける」を「支援する」と読み替えることで、ドライカースの言葉が持つ意味が、より温かく、そしてアドラー心理学の思想と深く結びつくように感じられます。
「支援する」には、こんな意味合いが込められていると思います。
- 内発的な動機付けを促すこと: 「やりたい」という子どもの気持ちを大切に育む手助け。
- 適切な情報や機会を提供すること: 子どもが自分で考え、決断するためのヒントを与えること。
- 勇気づけ、そして信頼すること: 子どもの可能性を信じ、小さな一歩を後押しすること。
- 成長のための安全な環境を整えること: 子どもが安心して学び、試し、成長できる場を作ること。
アドラー心理学が「相手を変えようとしない」と説くのは、他者の課題を尊重し、その人が持つ力を信じるからこそ。そして、ドライカースの「仕向ける」は、まさにその「勇気づけ」と「信頼」に基づいた、積極的で建設的な「支援」の形なのではないでしょうか。
こうして考えてみると、ドライカースの言葉とアドラー心理学の前提は、決して矛盾しているわけではなく、むしろ同じゴールを目指すための、異なる角度からの表現だと理解できるようになりました。
もし私と同じように「仕向ける」という言葉に戸惑いを感じた方がいらっしゃったら、ぜひ一度、「支援する」と置き換えて読んでみてください。きっと、また新しい発見があるかもしれません。
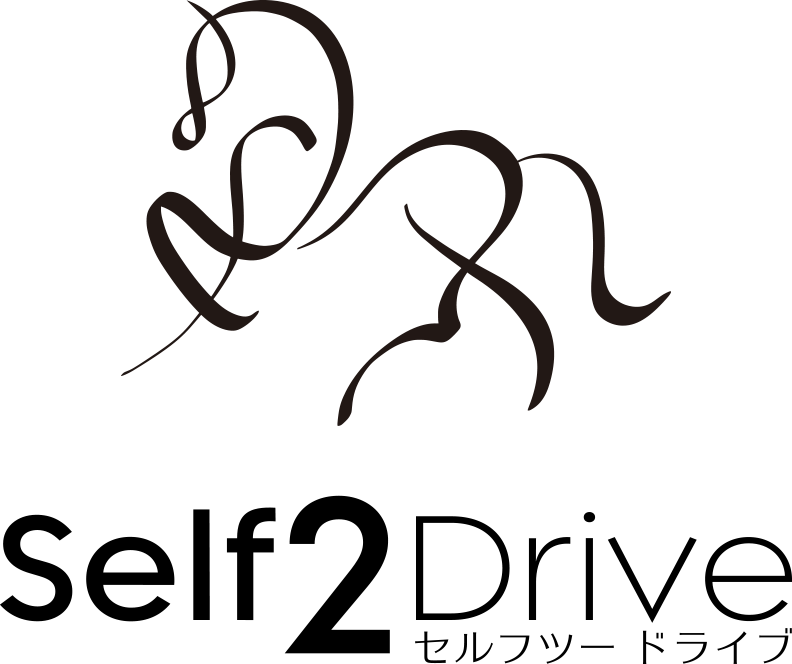
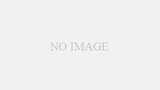
コメント