アドラー心理学の中心的な概念のひとつに「勇気づけ(Encouragement)」があります。これは、相手が自己の価値を感じ、自らの力で課題に立ち向かう力を持てるようにサポートする関わり方を指します。
そもそも「勇気」とは何か?
アドラーさんが定義した「勇気」とは、「困難を克服する力」のことです。私たちが人生を歩む中で、さまざまな困難や課題に直面します。そのとき、恐れや不安に負けるのではなく、それを乗り越えて前進する力こそが「勇気」です。
アドラーさんは、私たちが健全に成長し、充実した人生を送るためには、「共同体感覚(社会と調和しながら生きる意識)」を持ち、その中で自己の役割を果たせることが重要だと述べています。そのためには、自分を信じて行動する勇気が不可欠なのです。
「怒るのでも、褒めるのでもなく、勇気づける」とは?
アドラー心理学では、「叱ることや褒めることは、上下関係を生むため望ましくない」とされることが多いですが、これを誤解して「叱るのも褒めるのもNG」と極端に考えてしまうと、本来の「勇気づけ」の意図を見失ってしまいます。
勇気づけとは、「相手が自らの力を信じ、自発的に成長できるようサポートすること」です。そのため、関係性や状況によっては、叱ることも、褒めることも、勇気づけになることがあります。
叱ることが勇気づけになる場合
アドラー心理学における「叱ること」とは、単に感情的に怒ることではなく、相手の成長を信じて伝える「建設的なフィードバック」のことです。例えば、子どもが努力を怠り、困難から逃げようとしているとき、「あなたらしくない、逃げずに向き合おう」と伝えることは、勇気づけになります。
また、職場や教育の現場で、部下や生徒が無責任な行動を取った場合、毅然とした態度で「このままでは周囲に影響を与えてしまう。どうすれば責任を持てるか考えてみよう」と伝えることも、相手の自立心を育む勇気づけの一環です。
重要なのは、相手を否定するのではなく、相手の可能性を信じた上で伝えることです。単なる叱責ではなく、相手の成長を促す関わり方こそが、勇気づけとしての「叱る」なのです。
褒めることが勇気づけになる場合
一方で、アドラー心理学では「褒めることは上下関係を生むため、望ましくない」とされることが多いですが、それもケースバイケースです。例えば、職場の上司が部下に対して「このプロジェクトでの君の貢献はすごかったよ!」と具体的な努力を認めることで、部下の自信につながり、さらなる成長の原動力になることがあります。
ただし、「すごいね!」「えらいね!」といった表面的な褒め方は、「認めてもらうために頑張る」という依存心を生む可能性があるため、注意が必要です。勇気づけとしての褒め方は、「あなたが○○したことで、△△という成果が生まれた」と、相手の行動や努力といったプロセスに焦点を当てることが重要です。
勇気づけのポイント
勇気づけを実践するためには、以下のようなポイントを意識するとよいでしょう。
- 相手の価値を信じる
「この人には成長する力がある」と信じることが、勇気づけの第一歩です。 - 行動や努力を認める
結果ではなく、プロセスに焦点を当てることで、相手が自発的に行動できるようになります。 - 主体性を尊重する
相手が自ら出した考えや行動を尊重することで、さらに自ら考え、行動できるようになります。失敗から学ぶこともあります。相手の力を信じて見守ることも大事です。相手が協力を求めてきた時には一緒に考えましょう。 - 安心感を与える
失敗しても大丈夫だという雰囲気を作ることで、チャレンジしやすくなります。
まとめ
アドラー心理学の「勇気づけ」は、単に優しく励ますことではなく、「相手が自分の力を信じ、主体的に行動できるようサポートすること」です。時には叱ることも、時には褒めることも、その目的に沿っていれば勇気づけになります。
大切なのは、相手との関係性の中で「私はあなたの可能性を信じている」というメッセージを伝え続けることです。それこそが、アドラーが目指した「勇気づけの関わり方」なのではないでしょうか。
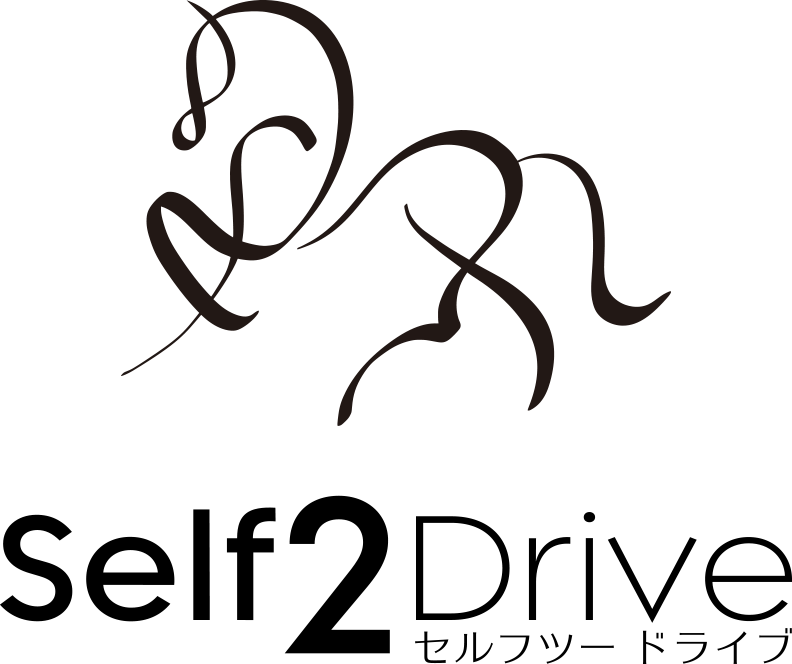
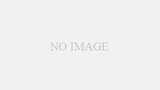
コメント